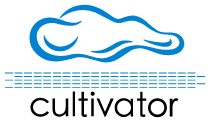宮嶋泰子、女性スポーツについて大いに語る。女性アスリート支援委員会の掲載記事を転載(1)日本の現役トップ選手にはない「妊娠、出産、子育て」のライフイベント
日本の現役トップ選手にはない「妊娠、出産、子育て」のライフイベント
~実業団が活動母体のシステムに問題点も―女子マラソン界~―女性トップ選手の苦心・奮闘を密着取材 宮嶋泰子氏―(1)
テレビ朝日でアナウンサー、キャスター、ディレクターとしてスポーツ報道やニュース番組で活躍し、計19回の五輪現場取材を通じて多くの内外有力選手を密着取材してきた宮嶋泰子さん(一般社団法人カルティベータ代表理事)に、女性特有の悩みを抱えながらも世界の頂点を目指してトレーニングに励んだ女子トップ選手の知られざる苦心・奮闘ぶりを語っていただきました。スポーツドクターの先駆けとして長年活動され、国立スポーツ科学センター長なども歴任された「一般社団法人女性アスリート健康支援委員会」の川原貴会長にオブザーバーとして参加していただきました。

宮嶋さん(左)と川原会長
川原会長 宮嶋さんは女性アスリートに広く関わってこられました。健康問題に限らず、女性アスリート全般について宮嶋さんにお伺いしたいと思います。
―宮嶋さんは長年、五輪・パラリンピック等を通じて数多くの女性アスリートを取材されました。女性アスリートの苦労とか悩みといったものを現場取材の中で見聞きされた経験を踏まえ、女性アスリートの手助けとなる助言をお聞かせください。
「私が一番気にしているのは、女性には結婚とか妊娠、出産、そして子育てというライフイベントをどうやってアスリートとして乗り切るかというロールモデルが、長い間、日本の中できちっとなかったことです。例えば、1964年の東京五輪の体操競技を見てみると、池田敬子さんも小野清子さんもお子さんがいらっしゃいました。そういう環境でも体操に取り組み、チームで銅メダルを獲得されました。ただ、その後のミュンヘン五輪でオルガ・コルブト(旧ソ連)が出てきて体操競技は変わってしまいました。連続する宙返りなど、角兵衛獅子のような動きは子どものような小さい体でないとできないので、過度な体重制限、摂食障害という問題も出てきました。競技が変質してきたことで起きてくる病気や問題もあります。ランナーもそうですが、ある一定以上のタイムを出すようになると、運ぶ荷物は少ない方が良いとばかり『痩せている方がいい』となって摂食障害になったりします。何か競技の概念が大きく変わるときに、いろんな問題が出てくるのかなと強く感じます」

第1回東京国際女子マラソン日本選手トップ7位の村本みのるさん
◇東京国際女子マラソンの初期が女性スポーツの黎明(れいめい)期
―東京国際女子マラソンが日本で初めて開催されて以降、女子マラソン界は大きく変わりました。
「私が、なぜ女性のライフスタイルや女性アスリートのことを考えるようになったかというと、東京国際女子マラソンがきっかけです。この女子マラソンは1979年に始まりました。第1回と第2回の連覇を果たしたのはジョイス・スミス(英国)さんで、1500mの五輪選手で欧州選手権3000mのメダリストでもあるトップアスリートでした。そういう人もいれば、日本人で最高位となったのが村本みのるさんという一般のジョガーでした。この大会で面白かったのは、海外も国内の選手もトップとジョガーが混在していたことです。ニュージーランドの選手に『仕事は何ですか』と聞くと、何と建築の現場監督でした。ジョギングが好きでマラソンを始めたそうです。さまざまな職種の人がいて、一斉に出てくるところが、まさに女性スポーツの黎明(れいめい)期と言え、そこで見えてきたものが、すごくおもしろかったですね」
―東京国際女子が始まったころには、ママさん選手はいらっしゃいましたか。

東京国際女子マラソン日本人として初優勝した佐々木七恵さん
「当時、東京国際女子マラソンには来なかったのですが、イングリッド・クリスチャンセン(ノルウェー)という選手がいて、元々クロスカントリースキー選手でしたがマラソンに転向し、世界記録も出して、息子さんを出産されて、ご主人と一緒に世界中の賞金レースを回って生活している人が現れました。一方、日本では、出産経験のある方を捜してみると、村本みのるさんや松田千枝さんら、一般のジョガーからマラソンランナーになった方々がいらっしゃいました。要するに普通に生活している人たちが、ちゃんとライフイベントの中にスポーツを入れていました。だから妊娠、出産、子育ても普通に経験してスポーツをやっているんですね。ところが、佐々木七恵さんのように、長距離のトラックを専門にやっていたアスリートが距離を伸ばしてマラソンにいくようになると、そのライフイベント、生活というものが全くなくなってしまいます。これですと分母もアスリート、分子もアスリートになります。分母は普通の生活者というのが村本みのるさん、松田千枝さんで、一般のジョガーの人たちは楽しんでスポーツをしているし、ライフイベントもクリアしてきています。分子にランナー、ジョガーというのが出てくるわけです。でも海外を見ますと、意外と分母がしっかりしてライフイベントもこなして、分子にアスリートという人たちがいます。クリスチャンセンやリサ・マーチン(豪州)がそうでしたね」

2009年、東京マラソンでゴールした弘山晴美さん(左)。右は夫で監督の勉さん
◇実業団ランナーは分母も分子もアスリート 摂食障害の温床に
―日本の実業団というシステムですと、女性アスリートにどのような影響がありますでしょうか。
「その後、日本では他の競技同様、実業団がマラソンの活動母体になっていきます。実業団は同じ宿舎で寝泊まりをして合宿を繰り返すところが多いですね。合宿所形式でやらずに個人でやるのは資生堂くらいかもしれません。資生堂は自分たちで生活して、合宿をやったとしても、たまに集まるだけで、他の実業団の様に合宿所でみんな同じ食事をしてという生活を365日繰り返す形ではやりません。この実業団の合宿所というシステムが、いろんなものを生んでいると思います。そこにいる段階で、分母も分子もアスリートになってしまう。このインタビューが始まる前に川原会長と話したのですが、そういう中では、少なくとも合宿所にいる間は結婚、妊娠、出産なんて考えないと思います。そうでなく、資生堂のようにサポートはするけれど、一人ひとりが自分の生活をしながらトレーニングをするという形、例えば、弘山晴美さんのように、ご夫婦で生活しながらトレーニングをして、リタイアされてから出産されましたが、そういう形ならいいのですが、どうしても合宿所生活で制限を受けるのが日本のアスリートなのだろうなと思っています。その一つとして私が感じたのは、見えない競争というのが合宿所ではあることです。『私は誰々さんに負けたくない』という気持ちが生まれてきて、摂食障害などになるケースもあります。インタビュー前に川原会長が熱中症のケースでおっしゃっていたのは、一人で走っていれば暑いから止めようとなるのですが、みんなで練習しているから我慢して止めずに走ってしまうという事例も起きています。摂食障害に加えて、妊娠、出産、子育てというライフイベントを無視してしまう状況以外に、悪いところというか、海外との違いはありますでしょうか、川原会長」
川原会長 選手の故障があります。どうしてもトップアスリートになると選手は故障を隠す傾向があります。
―陸上のケースですと、海外はクラブチームが主流で、日本は企業・実業団の中で競争をしています。日本と海外でスポーツ文化の違いはありますでしょうか。
「米国のクラブでも、その中で葛藤があります。セクシャルハラスメントに関する『ガールズ』という本を読みましたが、体操競技のクラブでも激しい戦いがあって、その中で一番にならないと州の大会、全米の大会に連れて行ってもらえないようなところでは、みんなケガを隠すし、コーチに罵倒されるのが嫌で黙っているなど、いろんな問題が出ています。それはクラブだけの問題ではなく、指導者がどういう人かということが次に問題になってくると思います。だからシステムと同時に、それをコントロールする監督・コーチが、どういうアプローチや考え方で選手に接するのか、そこが大きいと思います」(了)

宮嶋泰子(みやじま・やすこ) テレビ朝日にアナウンサーとして入社後、スポーツキャスターを務め、スポーツ中継の実況やリポート、ニュースステーションや報道ステーションのスポーツディレクター兼リポーターとして活躍。 1980年のモスクワ大会から平昌大会まで五輪での現地取材は19回に上る。2016年に日本オリンピック委員会(JOC)の「女性スポーツ賞」を受賞。文部科学省中央教育審議会スポーツ青少年分科会委員や日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ育成委員会委員、JOC広報部会副部会長など多くの役職を歴任。20年1月にテレビ朝日を退社、一般社団法人カルティベータ代表理事となる。
(2022/10/07 05:00)
その② 出産後の子どものケアは誰が?