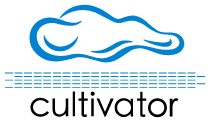時代の中で変わる「ダンスに求められるもの」
Reported by 宮嶋泰子
1.コロナ禍の日常生活の中で
これほど長くStay at Home が強いられるとは誰が想像しただろうか。直接顔を合わせる会議は中止されて全てリモートで行われる。人が集まるイベントもほとんど中止。家の中から一歩も出ないという日も少なくない。これまで通勤通学、さらには買い物等、私たちは意識をしないままに自然に身体を動かしていた。それが制限されるようになって初めてその重要性に気付くこととなった。
こんな時だからこそ身体運動をしようと家の中でもできるエクササイズがYouTubeに次々にアップされている。これは楽しそうだと目を引いたものはいずれもダンス系。ラテン音楽に合わせて踊りながらエクササイズをするズンバ。さらにはもっとゆっくり美空ひばりの歌謡曲に載せて踊るレクダンス。さらにはヒップホップ系のダンス。YouTubeでは手軽に世界各地のダンスも見ることができ、アフリカの子どもたちが天真爛漫に踊る姿には時間を忘れて見入ってしまった。

ダンスは太古の昔から世界中のあらゆる地域に存在すると言ってもよい身体表現で、神に祈りを捧げたり、五穀豊穣を祝ったり、人類の生活の中で大切な役割を担ってきたものだった。日本では明治から大正にかけて女子教育の一環として学校での身体づくりに使われてきた。さらにダンスは芸術にまで昇華されて現在に至っている。
ダンスは長い歴史を経て時代のニーズの中で様々に変化してきたわけだが、今やコロナ禍の中で運動不足解消のための身体運動という形で人々の生活の中に入ってきているようにも感じる。
それにしても今の日本も含めて世界はちょっとしたダンス天国かもしれない。 テレビをつければ、アーティストたちが歌と踊りとのコラボレーションで自身の魅力をアピールしている。 EXILEやK-POPのように、振付があって皆がダンスを合わせて歌うのが当たり前になっている。それを見て育った子供たちはその踊りを真似ながら成長している。 歌い踊る自らの姿をTickTokに投稿している子どもも少なくない。さらには学校ごとに発表されるダンスの映像がYouTubeにはあふれている。もはやダンスはごく一部のパフォーマーのためにだけにあるものではなくなってきているようだ。
2.小中でのダンスの必修化で見えてきたもの
表現運動、ダンスが必修となった。これによって様々な変化が表れたようだ。体育教科の中には勝敗を決める競技が多い中で、ダンスだけはどんな子どもたちも勝ち負けなく自然にチャレンジできる。最初の授業でできなかったことが徐々にできるようになる面白さに目覚めていく生徒も少なくない。できなかったことができるようになる喜びを体得させることはダンスが授業に取り入れられた目的でもある。
しかし指導する立場としては戸惑いがあるのも当然だ。ダンスの指導などしたことがない教師がほとんどだからだ。そんな中、ある高校の体育教師にとても興味深い話を聞いた。
教師にとって、ダンスは「怪我をしない」ので、他のスポーツの指導と比べると気持ちが楽だという。最近は習い事としてダンスを習っている生徒も多いので、生徒を数人のグループに分けるとそのうちの一人か二人はヒップホップやバレエの経験者だ。そうした生徒が中心となって自主的に作品を作るような仕組みを作り、生徒の自主性に任せる授業をしているという。自分たちで相談しあいながら一つのものを集団で作り上げていくプロセスが教育的に大きな意味を持っていることは言うまでもない。では教師は何をするのか。最近はYouTubeでよい作品がアップされているので、それを見せて参考にさせたり、本人たちが気付かない点をアドバイスしたり、作品が完成した時にビデオ撮影をしたりと、教師は生徒たちのアシストに回る形だ。生徒たちは普段の授業ではなかなか得ることができない「自主性」を認められて、とても楽しそうに自主練習も行っているという。
覚えることを中心に進められる日本の学校の授業の中で、自主性を重んじられるダンスの授業は生徒たちにとって生涯で最も印象に残る授業となりうる可能性を持っている。
3.総合型地域スポーツクラブで
文部科学省が推奨して平成7年から育成が行われて、現在は全国に3600余りある総合型地域スポーツクラブは、多世代、多種目、多志向をうたい文句にして、各市町村に一つは作りたいと育成が進められてきた。この総合型地域スポーツクラブを覗いてみると一般の市民が何を身体運動として求めているかがよくわかる。地元住民が通ってくれて笑顔で帰っていくクラブ作りにダンスは欠かせないものになりつつある。ダンスを取り入れるクラブには子どもから高齢者まで女性を中心に安定した参加者が集い、クラブ運営の基礎固めにも役立っている。今やダンスを取り入れていないクラブを捜す方が難しいかもしれない。
今回はチアダンス、フラダンス、ヒップホップをそれぞれ取り入れて成功しているクラブの様子を見ながら考えてみたい。
4.チアダンスで家族も地域も楽しく
2017年に岐阜県にできた一般社団法人スポーツリンク白川は、既存の白川町体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ(チャオ白川スポルトクラブ)が一つの団体となって法人設立したものだ。ここでクラブマネージャーを務める渡辺靖代さんはチャオ白川スポルトクラブで14年程前からチアダンスを指導してきた。もともとエアロビクスのインストラクターだった渡辺さんだが、チアダンスの指導者になる転機はある子どもたちのパフォーマンスを見たことだった。初めて3歳から5歳の児童のチアダンスを見た時の衝撃をこう語る。
「この年齢の場合、一般的にはお遊戯として先生が前に立って子どもたちがそれを真似るという形を取るんですけれど、そのチアダンスの子どもたちは違ったんです。先生が前でお手本を示していなくても、ボンボンを持ちながら踊っていたんです。これは凄い!と本当に驚きました」
渡辺さんはYouTubeなどで独学し、早速これを取り入れることとした。
大切なのはリズム感。ぽんとトン、ととんとトンなど、いつもの表だけのリズムに裏のリズムも加える。将来どんなスポーツをするにしてもリズムが大切だからだ。総合型地域スポーツクラブは多種目と唱っているので、将来の運動のきっかけづくりと考えているとのこと。
子どものチアは、5回、10回で一区切りをして、小さな発表会をしていくと、その過程で子どもたちが自己表現ができるようになって自信をつけていくのが手に取るようにわかるという。

子どもたちがチアの発表会に向けて動き出すと、お母さん等家族が子どもたちの発表会のために衣装を縫ったり髪飾りを作ったりと忙しくなり、いつしか発表会は家族全体のイベントとなってくる。
さらに進んで、自分たちもやりたいというお母さんたちも現れ、大人のクラスも開設された。「子育てだけではない輝いているお母さんの姿を家族に知ってほしい」をコンセプトにして、普段着ることのない衣装に、お化粧をしてステージに立ち、みんな生き生きと踊った。子どもと母親が一緒に舞台に立つ様子をお父さんがビデオに収めている家庭もあった。祖父母も孫の姿に目を細め、チアダンスで家族が一つになる様子を見るのは嬉しいものだ。 渡邊さんは、最近、65歳から80歳の人を対象にした高齢者チアにもチャレンジしている。不思議なことに普段は手を挙げると肘が曲がっている人が、ボンボンをもって鏡の前でポーズをすると、なんと肘が伸びているのだそうだ。鏡の前で踊るということをこれまでやったことがなかった人たちだが、「皆で一緒にやると実に楽しい」と言って、
各人が家で練習をしては週に一度の合同練習に精を出すという。集まっての練習も距離を取ってのソーシャルディスタンス。コロナ禍でも大切な運動としてとても重宝がられているとのことだった。

5.ゆったり気分で楽しむフラダンスはフィットネス
茨城県つくば市にある認定NPO法人日本スポーツアカデミーのクラブマネージャーをしている根本慶子さんによれば、フラダンスを導入したのは一年前のことだという。
学童保育をクラブで行っていることもあり、放課後の子どもたちの活動をどうするかが一つの問題だった。活発な子供たちには陸上競技やバドミントンをさせておけばよかったが、どうしてもスポーツになじめない子どもたちがいた。それは幼児の頃からゲームばかりやっていて運動習慣がなかったり、肥満気味の子どもたちだった。運動で人と競うと負けるというのが頭にあるので負けることをしたくないというのだ。男の子の場合はスポーツに苦手意識を持っていても、リレーや鬼ごっこ形式、団体戦にして、個人の力がわからないようにすると全員で勝つことを目指せるが、女の子は精神年齢が高いこともあり、そうしたごまかしは効かないという。女の子は全体が勝っても自分は遅かったという意識を引きずってしまうようだ。

スポーツ実施率を何とか上げたいと思っていた根本さんはある時、運動を好まない女の子たちも音楽が鳴ると自然に身体を動かすことを発見。これがフラダンスを導入するきっかけとなったのだ。
フラダンスは動きがゆっくりなだけに子どもたちには簡単に見えるようだ。パウスカートをはくと女の子たちのテンションが急に上がってくる。音楽とパウスカートの魔法にかかって、子どもたちが自然と動き始るのだ。
フラダンスを始めた女の子たちの変化は著しかった。 「ほとんど発言しないシャイだった子どもが自分を出せるようになってきた」というのだ。ダンスは自己表現だ。自分の内なるものを体の外に出すことを続けるうちに、子どもたちの中で変化が生まれてくるのだろう。またフラダンスを通じてハワイ語に興味を持って、自分たちで勉強するなど、日ごろやったことのないものに挑戦する積極性も身に着いていくようだ。
ハワイアンの癒し効果のある音楽に合わせて、手と腕の動きで言葉を表現しているフラダンスはその意味するところが分かってくると、大人には心に沁みるものがある。ダンスというカテゴリーで行うと躊躇してしまう人もいるので、フィットネスという感覚で、ベーシックで簡単な曲で振りを覚えていく。ダンスは人に見せるものというイメージがあるが、ここでは自分の健康のために身体を動かすという感覚を大切にしている。恥ずかしさを払しょくして、上手下手は問わない。

コロナ禍の下で少しでも運動をしたいと望む人々にはダンスをフィットネスと考えて行うのが最も簡単な方法だろう。人々の日常の中にこうした形でダンスが入り込んでいくのだ。

6.ヒップホップでダンスは男女が楽しむものに
どうしてもダンスは女子のものというイメージが長いあいだ染みついていたが、ヒップホップダンスが流行してからは、男女が共に楽しめるものとなってきた。ジェンダー平等という意味からも同じダンスが男女でできるのは楽しいことだ。
スピードスケートで数々の世界記録を塗り替えている平昌五輪のメダリストでもある髙木美帆、菜那姉妹は子どもの頃からヒップホップを習っていた。そのリズム感が生かされてスピードスケートの頂点に立っているともいえる。
今やダンスはあらゆるスポーツの動きの基本を作るものとなり、より多くの人々が健やかな人生を求めて行うものに変わってきているのだ。

以上、女子体育2020年春号に掲載されたものを転載。

執筆者紹介:宮嶋泰子

スポーツ文化ジャーナリスト 元テレビ朝日スポーツコメンテーター (一社)カルティベータ代表理事
テレビ朝日にアナウンサーとして入社後、スポーツキャスターとして仕事をする傍ら、スポーツ中継の実況やリポート、 さらにはニュースステーションや報道ステーションのスポーツディレクター兼リポーターとして自ら取材し企画を制作し続けてきた。
1980年のモスクワ大会から平昌大会までオリンピックの現地取材は19回に上る。43年間にわたってスポーツを見つめる目は一貫して、勝敗のみにとらわれることなく、 スポーツ社会学の視点をベースとしたスポーツの意味や価値を考え続けるものであった。2016年には日本オリンピック委員会からの「女性スポーツ賞」を受賞。
1976年モントリオールオリンピック女子バレーボール金メダリストと共にNPOバレーボール・モントリオール会理事として、 日本に定住する難民を対象としたスポーツイベントを10年以上にわたり開催、さらには女性スポーツの勉強会を定期的に行い、 2018年度内閣府男女共同参画特別賞を受賞。
社外の仕事として文部科学省青少年中央教育審議会青少年スポーツ分科会委員や日本体育協会総合型地域スポーツクラブ育成委員会委員、 日本オリンピック委員会広報部会副部会長、日本障がい者スポーツ協会評議員他、多くの役職を務める。