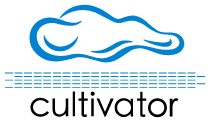第18回女性スポーツ勉強会「よりよく生きるための身体と社会のつながり」

稲澤裕子氏、高尾美穂医師、木下潮音弁護士、宮嶋泰子カルティベータ代表、岡崎朋美氏、伊藤華英氏
カルティベータ・第18回女性スポーツ勉強会「よりよく生きるための身体と社会のつながり」
女性をとりまく社会へのさまざまなアプローチを共有しようと、第18回女性スポーツ勉強会「よりよく生きるための身体と社会のつながり」が1月27日、ビジョンセンター浜松町で開催された。ライブ配信に加え、50名以上の参加者で会場は満席。「スポーツから社会を変える」をテーマに、各専門家から貴重なエピソードが紹介された。
冒頭で、ファシリテーターの宮嶋泰子さん(カルティベータ代表理事)が「この勉強会は2014年に始まり10年目。毎回、目から鱗が落ちるような驚きの連続でした。今回も多くの学びを得たいと思います」と話し、5名の登壇者について紹介した。
「女性アスリートが長く続けられるアプローチを」伊藤華英さん「1252プロジェクト」

最初の登壇者は、元競泳選手の伊藤華英さん。北京、ロンドン五輪に出場し、現在「1252プロジェクト」を推進している。このプロジェクトは、『生理×スポーツ』の課題に向き合い、アスリートや指導者への情報発信をしていくプロジェクト。1年間52週のうち、約12週間は生理期間にあたることから、この名前をつけた。
「このプロジェクトを始めたきっかけは、私自身が競技時代に月経の不調でさまざまな経験をしたことにあります。当時は、生理については人にシェアしないもの。2004年のアテネ五輪をかけた3月の選考会、私は生理前で、なぜか涙がぽろぽろ出てくる。自分でも理由が分からず、その五輪切符は掴むことができませんでした。4年後の2008年、こんどは北京五輪への出場を決めたのですが、月経を計算したら、オリンピック期間がすべて生理期間に当たるとわかりました」
周りに相談することが出来ないまま、婦人科を受診し、中容量ピルの服用を決めた。
「私の場合、生理前は体重が増えて、始まったら減るのですが、当時はレーザーレーサー(身体に密着する水着)もあり、本番に体調を合わせなければなりません。単に生理期間をずらずという知識で中用量ピルを飲みました。その結果、体重が4〜5kg増えてしまい、腹圧も入らず、月経前のようなメンタルに。本番では不安をコントロールできずに終わりました」
しかし、伊藤さんはピルを否定しているわけではない。こう説明する。
「ピルを飲んだことが悪かったのではありません。知識が無かったんです。自分のコンディションについて把握し、コーチと話し合い、知識を持ってピルを使えば良かった。現在では副作用の少ない低用量ピルを服用する選手も増えてきています」
生理に対する知識の必要性や、情報共有の大切さに気づいた伊藤さんは、2021年から「1252プロジェクト」を開始。学生アスリートをメインに、授業を行ってきた。
「なぜ学生なのかというと、骨の成長期である10代への啓発が最も重要だからです。女性の身体は20歳に骨量がピークになるため、10代に無月経の時期があると、骨の形成不全から骨折しやすい身体になってしまいます。日本は生理についてタブー視する傾向があり、スポーツの現場では『生理が来なくなったら一人前』といった間違った考えすらあります。トップアスリートが自分の経験を話すことで、学生にとっては親近感があり、真剣に耳を傾けてくれているなというのを感じています」
また、指導者への知識共有もスタート。そのツールとして、『1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定』を今年3月から開始する。
「選手は『月経で休んだらレギュラーから外される』という不安も抱えるもの。女子アスリートが、健康に楽しくスポーツを楽しめる環境を作るためには、指導者に知識を身に着けていただくことも必要です。特にスポーツでは男性コーチが多く、むしろ男性コーチ側も知識がなく悩んでいるかも知れない。この検定を入り口に、プロフェッショナルな指導のなかで、女子アスリートのパフォ―マンスをもっと上げていくヒントにして欲しいと思っています」
最後に伊藤さんは、「女性アスリートが長く、一生続けられるようなアプローチを手助けできればと思います」と話した。
「体が変わる成長と、アスリートとしての成長を、同時に叶える」高尾美穂医師

続いて登壇したのは、スポーツドクターで産婦人科医師の高尾美穂さん。
「私がスポーツドクターになった2010年には、まだスポーツドクターといえば整形外科やリハビリテーション科の医師が8割で、産婦人科医は100名ほど。産婦人科のスポーツドクターは、試合に帯同するのではなく、試合の日をうまく迎えるためにバックで支える役割です。また私自身は普段、クリニックの医師としても働いていますが、産業医としての就業支援も、スポーツドクターも、同じ役割を感じています。アスリートは、自分のコンディションを落とさないことで、パフォーマンスを上げられる。一般の人も、自分がやりたいことのために、コンディションを保つことが大切になると考えています」
そして男女の身体の違いについて説明した。
「まず一番の差は骨格、なかでも骨盤に違いがあります。女性は赤ちゃんが生まれる出口があるために骨盤の横幅が広く、大腿骨が膝に向かって斜めに刺さる形になります。男性の足は、骨盤から膝にむけて一直線に近い。女性のほうが物理的に、膝の怪我をしやすい身体になっているのです。その他にも、貧血、肩こり・腰痛・関節症など、女性に多い疾患は生涯スポーツを続けていく上で影響があるでしょう」
その上で、女性ホルモンの働き、生理が起こる仕組み、月経困難症や月経前症候群(PMS)、低用量ピル、無月経と骨密度など、多岐にわたる知識を、わかりやすく解説した。
「生理痛は我慢することではなくて、『対策するべき課題だ』と認識することがまず大事です。痛み止めもありますし、低用量ピルは、日本では1999年に避妊目的で認可されましたが、今では生理痛や子宮内膜症の対処として保険適用されるようになりました。まずは生理を理解すること。生理を知ればスポーツも、人生も、もっと楽しくなります」
そして「女性の人生は、女性ホルモンに揺さぶられる」として、こう提言を続けました。
「生理について単に『血が出る』という知識ではなく、人生にとって大切な体の変化が起きていることを、家庭や学校での性教育として伝えなければなりません。体が変わっていく成長と、アスリートとしての成長を、同時に叶えていくことが必要だということを、指導者も本人も知ることが大切です」
医師の視点から、分かりやすく正確な多くの情報を提供してくださった高尾さん。最後にスポーツドクターの視点から、こう話しました。
「性教育というとハードルが高くなりがちですが、スポーツの世界でコンディションを高めるための提案、というと、性教育の分野も含めることになり、話しやすくなる。性教育と言わずに、斜めに切り込んでいくことも1つの伝え方なのかなと思っています」
岡崎朋美さん「一般の女性が育児も仕事もやるように、育児とアスリートをしたい」

次に、スピードスケートの岡崎朋美さんが、妊娠・出産をへて現役復帰した経験について語った。
岡崎さんは94年リレハンメル大会から2010年バンクーバー大会まで、オリンピック5大会連続出場。長野大会では銅メダルを獲得した。また、2007年に結婚し、バンクーバー大会後には、妊娠・出産をはさんで2014年ソチオリンピックにチャレンジすることを決意した。
「計画的に考えました。2010年2月のバンクーバーオリンピック後、すぐに子供が出来なければ、間に合わずに引退になる。すぐに妊娠することが出来たのは、本当に良かったです」
妊娠期間中から、手探りの日々だった。
「当時、アスリートの妊娠についてまったくデータがなく、出産前後はしっかり6ヶ月ほど休みました。『お腹の赤ちゃんの分まで』と思って、ご飯をいっぱい食べていたら太りすぎてしまい、出産前からウォーキングを始めました。出産後もまずは脂肪を落とすことから。『アスリートの妊娠・出産の時はこういうトレーニングしましょう』という情報が、海外の選手にはあるのですが、日本には無かったんです」
現役のスケート選手による育児も、前例がなかった。
「当時、JISS(国立科学スポーツセンター、北区)には託児所があったのですが、私の場合はスケートリンクがある山梨で練習している。ベビーシッターを私だけのために雇うとお金がかかりすぎるので、私は一人で、育児も練習もしなければならない状況でした」
また母とアスリートを両立したいという思いもあった。
「ソチ五輪までの期間、赤ちゃんを他人に預けることも提案されました。でも、それじゃ意味がないんですと言いました。私は一般の女性が育児も仕事もやるように、育児とアスリートをしたかった。自分が納得いく育児をやるために、離乳食を練習場に持っていって育児と並行する、というような経験をしました。もちろん母や、義理の母も手伝ってくれて、乗り切ることができました」
自身の体験談を振り返りながら、こうまとめた。
「スポーツをやりたいけれど、子供がいるから出来ないというのは悲しいこと。むしろお母さん頑張ったね、と表彰されるのは何より嬉しいことです」

「ジェンダーギャップを埋めるためには、企業が変わらなければ」木下潮音・弁護士

次に、弁護士の木下潮音さんが法律の視点から、ジェンダー平等についての歩みを紹介した。まず男女雇用機会均等法について、1985年の成立から、1997年と2006年の改正をへて、現在に至る歴史を説明した。
「2006年以降、男女は平等になったでしょうか。いえ、世の中は変わっていません。今でも、企業や社会の重要な場面には女性が少なく、それが日本社会の停滞に繋がっています」
そして女性が輝ける社会にむけて、新たに制定されたのが女性活躍推進法(2015年9月25日、閣議決定)だと紹介。なかでも2022年7月の改正が画期的だったことを説明した。
「301人以上の企業が開示すべき情報のなかに『男女の賃金格差』が明記されました。企業にとってはびっくりなこと。ある企業では、全社員での賃金格差は、男性に対して女性は40%。これは大変な数字であり、男女の差が明確になりました」
続いて「妊娠・出産・育児」について、労働基準法の視点から解説。産前産後休暇、生理休暇の保障や、婚姻・妊娠・出産等を理由にした不利益取扱の禁止などを紹介。一方で、育児休業については、使えている人が少ないことを指摘した。
「制度としては世界トップランクの権利なのですが、使えている人が少ないのが現状です。育児休暇のほかにも、育児休業中の社会保険料免除や休業給付、新たな制度として『産後パパ育休制度』もあります。しかし実際の職場ではどうなっているか。女性正社員の育児休業は定着しましたが、非正規社員の場合は、有期雇用契約であるために育児休業がとりにくいなどの問題があります。女性労働者の60%が有期や非正規の社員であるため、女性間でも格差が生まれています」
そして、こうまとめた。
「労働者の保護を考えると、正社員で働きたい人は増えています。しかし女性が働くことを定着できていないのが現状です。日本のジェンダーギャップを埋めるためには、企業が変わっていかなければなりません。良い人に長く働いてもらうためにも、より良い使える制度を作っていけるよう、さまざまな企業に提案をさせていただいていきます」
稲澤裕子さん「情報開示の義務付けが、ガバナンスの源泉に」

最後に、元読売新聞記者で昭和女子大特命教授の稲澤裕子さんが、「スポーツ競技団体と女性理事」をテーマに登壇した。稲澤さんは日本ラグビーフットボール協会初の女性理事でもあり、各競技団体における女性理事の調査に尽力している。
稲澤さんは、女性スポーツ発展のための国際的戦略として、2014年に採択された「プライトン。プラス・ヘルシンキ宣言」について解説。その中でも重要な項目として、「2020年までに、女性理事の割合を40%に引き上げるべき」という目標が制定された、と説明した。
これを受けて、日本スポーツ庁が2019年に制定した「スポーツ団体ガバナンスコード」のなかでも、中央競技団体に対して「女性理事の目標割合40%以上」が明記されたことを説明した。
「日本で、女性理事の割合が明記されたのは、私が知る限り初めてのこと。世界ではすでにクオーター制導入などもある中、『目標』という緩やかではあるが一種のクオーター制に値するものといえます」と稲澤さん。
「4年に1度、達成出来ているのか、今後どうするのか、といった情報開示が求められ、不適合になると助成金減額になります。この制度により、日本オリンピック委員会の女性理事は2021年に40%に達し、2023年には日本スポーツ協会も45%を達成しました。情報開示を義務付けられたことが、ガバナンスの力の源泉になっていると考えられます」
そして稲澤さんはこうまとめた。
「世界各国で、ジェンダーストリームをベースに置いて社会を変えているなか、日本はジェンダー主流化が欠けている状況です。これからの女性理事達が、スポーツ界の好循環を生み出すための、循環の歯車を回す力になることが出来たら良いなと思っています」

最後に宮嶋さんが挨拶した。
「アスリートはいつも、自分の体と心と対話をし、内面を研ぎ澄ませていきます。アスリートを終えた後、誰もができるわけではない経験を社会に発信することで、社会のパワーに変えて欲しい。この『カルティベータ』を通じて、文化とスポーツを通じて社会を耕すお手伝いをしていきたいと思います」
次回の女性スポーツ勉強会(第19回)は、2024年7月6日に表参道の東京ウィメンズプラザで開催開催予定。



この事業は公益財団法人JKAの公益補助事業として行われました。